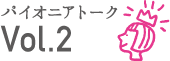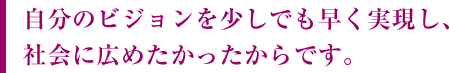荒木: 私の時代にはエンジニアリングの分野に進む女性は非常に少なかったのですが、先生が学生だった頃はどうでしたか。
玉城: 私が大学学部に行ったときには女性は多いと言われていたのですけれど、それでも全体の一割でした。60名中6名と少なかったですね。大学院に進むと更に5%程度になって、博士課程に進むともっと少なくなりましたね。
荒木: 先生の場合は沖縄で最初に情報工学を勉強されて、その後ご自身のやりたいことを求めて筑波大学などでさまざまな研究者のところに行かれたと聞いています。「この研究がしたい」という強い気持があったので、女性が少ない環境については特に違和感はなかったのでしょうか。そういう情熱というか、先生を駆り立てていたモチベーションが何だったのか、とても興味があります。
玉城: 「部屋の中にいながら部屋の外での体験をたくさんしたい」というモチベーションはずっとぶれていません。できるだけあまり外に出たくないという思いが強かったんです。でもそれは私だけじゃないようで、今世界的にも「引きこもり」の人が増えていて、日本だけの傾向ではなくなっているようです。日本国内では、心身ともに何か問題があって引きこもっているという人もいる一方で、できるだけ部屋の中にいていろいろな体験をしたいという人も増えています。それでソーシャルメディアやYouTubeのコンテンツが広まったりしています。最近のニュースでは、日本だけでなく、イタリアでも「引きこもり」が増えていると報じられていました。
荒木: イタリアでもそうなのですか。
玉城: 「引きこもり」が増えてどう対応していいかイタリアは困っているということで、「引きこもり」の多い日本の知見が活かせるのではと言われています。世界的にも、徐々に部屋の中にこもる人が増える時代になってきたのだと思います。そこで、引きこもり時代を悪いものとして捉えるのではなく、この時代において人類がどうやって発展してくのかを研究し、人類を発展させる「モノ」を作ることは絶対に必要なことだと思いました。私にとっても必要ですし、まわりにとっても、きっと必要な研究なのでどうにか実現しないといけません。さまざまな分野を調査し、研究してきました。そのとき、話すということはすごく大切だと思ったのです。話すことでモノが具体的になるというだけではなく、いわばひとつの考えを広める布教活動のようなことだと思うのです。
荒木: なるほど。
玉城: 研究者というのは、ある意味早すぎるイノベータ―だといえます。50年、100年先のことを見ている人です。研究者に「これからこういうモノが必要だと思うのですがどうですか」という話をするということは、未来に布教と同じなのです。その布教をモチベーションを高くもちながら、ずっと実践しています。
荒木: 先生の場合は大学で講義もされ基礎研究もされています。それと同時に起業してこういうすごい製品を作っています。技術をかたちにして、さらにそれを社会に出していく、その両方をやられていてとても大変だと思います。共同研究などの方法で自分の技術を世の中に出すというやり方もあると思うのですが、あえてご自身で起業することにどのような意義を感じておられますか。
玉城: そこですね。研究自体はもちろんひとつの文化になったり、ビジョンになったり、研究の知見によっていろいろな知識が蓄積されていくのですが、共同研究や共同開発で普及させようとすると、その研究者が意図しない方向に使われてしまう場合もあります。それはそれで社会に寄与したという面では重要なのですが、私自身は先程お話したようにビジョンを実現したい。それも少し早急に実現したいという思いがありまして、それで共同研究先を探すのに10年、20年、もしかしたら30年もかかってしまうかもしれないと考えると、自分で起業した方が早いと思いました。
荒木: 自分でやってしまおうと。
玉城: はい。研究者でも自分のビジョンを早めに実現したいという方は起業していらっしゃいます。
荒木: 技術とか研究の成果があったとしても、企業側がそれを使ってこういうことをしたいということと、研究者の側が考えているビジョンは、必ずしも一致しないケースもあるから、それだったら自分で世の中に広めていく方が良い。それが起業した大きな理由だということですか。
玉城: はい。

荒木: 「UnlimitedHand」を開発された時にクラウドファンディングで資金を集められたそうですね。クラウドファンディングでは、お金が集まることで社会にどれくらいニーズがあるかが分かったので、製品化に向けて確信が持てたと先生が話されていたのを聞きました。
玉城: はい。社会にこの技術のニーズがあるのかを調査するためにクラウンドファンディングを実施しまして、現在の社会ではニーズが徐々に増えてくるだろうと分かり、安心したというか、起業して良かったと思いましたね。
荒木: 逆に、ご自身がずっと変わらずもち続けているビジョンに世の中が付いてこないということを経験されたり、感じたりすることはありますか。
玉城: 博士過程の研究で、「PossessedHand(ポゼストハンド)」※というシステムを発表したのですが、それはコンピューターがヒトの手指の動きをコントロールするという研究でした。そういう機能は怖いと思われて、社会的なニーズは低かったです。 ※玉城氏が博士課程在学中の2010年に研究開発した、コンピューターによって人の手をコントロールする装置。その仕組みは、前腕の筋肉に電気刺激を加えることにより、手指や手首にある16の関節を動作させてからヒトの手指の動きを出力(コントロール)するもの。
荒木: なるほど。
玉城: 社会的なニーズに関する調査を分析してみると、「PossessedHand」はインタラクションがないという結果でした。
荒木: 一方的なところがネックになったのですね。
玉城: 研究としては将来的には双方向にするつもりでした。しかし当時は、ずっと「PossessedHand」で操られ続けるのではないかという恐怖心があったようで、怖いと言われました。本来はあの研究自体は「Body Sharing(ボディシェアリング)」といって、体をシェアしようという内容なのですが、体をシェアし合うのもちょっと怖いと評価されたようです。

荒木: そうですか。コンセプト自体が怖がられてしまったのですね。
玉城: その意味では、電話だって「Body Sharing」の一部ですよ。電話はもともとは遠隔地にいる人同士の耳のシェアでした。「PossessedHand」は手のシェアでしたが、そこが社会的には怖いということでなかなか受け入れてもらっていないですね。でもいろいろなSF映画や小説では体のシェアは当たり前になっているので、将来的には社会的に受容されるのではないかということで準備はしています。
荒木: 新しい技術は内容によってはすぐには受け入れられないことがあるかと思いますが、社会の皆さんに理解をしてもらって受け入れてもらえるようにするために、先生はどうされているのですか?
玉城: 私自身は受け入れられないとなったとき、じゃあどこまでなら受け入れられるのか調査をします。そして受け入れられるレベルには段階があるので、その段階を徐々に上げていくという手法を取っていますね。
荒木: 最初に「PossessedHand」を出されたときに皆さんがちょっと怖いと言っていた頃から比べると、世の中の意識が変わってきたなとか、人々が受け入れるようになってきたなとかいった手応えは感じられますか。
玉城: 感じますね。ゲームのキャラクターやバーチャルリアリティのキャラクターと体の動きをシェアする、シンクロさせることは今は当たり前になってきています。そしてその次の段階、今度はロボットと体の動きをシェアするというのも徐々に皆さんのイメージの中ではかたちになりつつあって、ゆくゆくは人間とロボットがBody Sharingして働くだろうということが受け入れられつつあると、ここ数年感じています。
荒木: それは、若い人達が子供の頃からそういった技術に慣れ親しんでいるということも大きいのでしょうか。
玉城: やはり若い頃から慣れ親しんでいる人は、受け入れることも早いですね。コンピューターサイエンスにずっと慣れ親しんでいる方は、バーチャルリアリティの操作に慣れるのが早いですし、ロボットの操作も同様のようです。
荒木: 女性と男性、あるいは年齢で技術の受け入れ度合が違うと感じることはありますか。
玉城: 「UnlimitedHand」の電気刺激に関する調査では、女性の場合は若い方が、男性の場合は年配の方が受け入れやすいという結果があります。ただ個体差がありまして、それによる外れ値は大きく出るので、やはり本人の心の持ちようだといえます。
荒木: 先生は日本だけではなく海外で研究されたご経験もありますよね。現在も海外の企業とも仕事されていますが、日本と海外とで新しい技術の受け入れ方の違いをお感じですか。
玉城: よくサンフランシスコに行くのですが、サンフランシスコと日本では技術の受け入れ方に差があります。日本国内で技術を受け入れるときは、社会的に需要があるかどうか、ビジネスチャンスになり得るかどうか、そしてユーザー視点から現代の問題を解決できるかどうか「問題解決型」で判断することが多いです。一方、サンフランシスコや中国や東南アジアでは少し違っていて、問題解決型やビジネスチャンスといった点に加えて、どう世の中にインパクトが与えられるかということで判断することが多いです。今は存在しないモノをどう生み出していくのか、今現在は需要がなくても、その潜在性を大きく見ているような気がします。
荒木: そのインパクトというのは、今までなかったような価値ということでしょうか。誰もが考えてもいなかった社会的な影響力を生み出す力という意味でしょうか。
玉城: そうですね。おっしゃる通り、新しい価値を生み出すというところは日本よりも世界の方が注目していると思います。
荒木: 日本もそういうふうになっていくと思われますか。
玉城: そうですね。これからそうなっていくといいなと私は思っています。
荒木: 企業などでもニーズ調査をするときに、お客さんになりそうな人とかに「どういう物があったら便利だと思いますか」と聞いても、新しい画期的なモノは生まれないとよく言われています。ですから、今までまったくなかったモノを創り出すイノベーションが必要なんですよね。
玉城: なかなか難しいところですね。新しい価値を生み出すイノベーションが重要だと私自身も思ってはいます。一方で、現実的なニーズがないと難しいとも感じます。ですので、その両輪をどうにか成り立たせるモノを研究し、開発していかなくてはならないでしょう。そのバランスがかなり重要で、難しいところですね。
荒木: 世の中で使ってもらうためには、ある程度現実的なニーズも必要ということですか。
玉城: そうですね。中庸ということですね。昔、研究だけをしているときにはイノベーティブなことだけやっていればいいと思っていたのですけれど、会社を立ち上げてみると「イノベーティブ」にプラスして「ニーズ」、そして「問題解決」のバランスを取らなければならず、苦戦しています。
荒木: 先生のお話を聞いていると、ニーズというところをすごく強調されていて、研究者と起業家の二足の草鞋(わらじ)を履いていらっしゃる感じがすごく伝わってきました。