「全米最優秀女子高校生を育てた教育法」
ライフコーチ
ボーク 重子 さん
基調講演 講演録
ライフコーチ
ボーク 重子 さん
イノベーションが進み新しい価値が生まれ、これまでのやり方や常識が通用しなくなりつつある今、私たちは次の世代をどのような教育方法で育てていけばいいのでしょうか。今、その課題を解決するキーワードのひとつとなっているのが「非認知能力」です。これは、子どもの幸せと成功に大きく関与していることがさまざまな研究で証明されており、アメリカなどではこの能力を伸ばす教育に移行しています。シンポジウムの基調講演ではこの非認知能力に基づく教育を実践し、全米最優秀女子高校生の娘さんを育てた、ライフコーチのボーク重子さんにお話をお伺いしました。非認知能力とはどのような力で、それは子どもたちをどのように変え、幸せや成功に導いてくれるのでしょうか。また非認知能力は、子どもを育てる親や大人にとっても必要な力だとボーク重子さんは語っています。ぜひご一読ください。
皆さん、こんにちは。ライフコーチのボーク重子でございます。ライフコーチとは、夢の実現をお手伝いする仕事で、アメリカでは大統領や大企業の社長から主婦や学生まで、パーソナルトレーナーを雇うのと同じくらい浸透している職業です。私はもともと現代アートの専門家で、アジア現代アート専門のギャラリーを30代後半に開いてそれから15年間ずっと突っ走ってきました。ギャラリーを開業するとき、何から始めていいか分からなかったのですが、そのときに助けていただいたのがライフコーチでした。それで、私も人生の折り返し地点になったら、ぜひこのスキルを1人でも多くの方にお伝えしたいと思って、ギャラリー経営の傍らライフコーチになる勉強をコツコツして、50歳のときに資格を取りました。
そしてもう1つの夢だった執筆活動を50歳のときに始めて、「ああ、人生の新しいチャプターが始まった」と思っていたら、我が家に大事件が起きたのです。私たちの娘が、なんと60年の歴史ある大学奨学金コンクール「全米最優秀女子高生賞」で優勝してしまったのです。このコンテストは各州と自治区の代表51人が「学力」「質疑応答」「自己表現」「体力」「特技」の5つのカテゴリーで評価され、その総合点で優勝が決まります。5カテゴリーの成績優秀者4名は別に表彰されますが、娘は、5つのカテゴリー全てでトップ4に入ります。これはコンテスト60年の歴史の中で初めてのことだったそうです。それで日米のいろいろなメディアから取材を受け、親の私まで「一体どういう子育てをされたのですか?」と、取材を受けるようになりました。
そこで私と夫の子育てを一冊の本にまとめたのが、2018年2月に出版された「世界最高の子育て」です。その中で私はどうして世界最高の子育てを探そうと思ったのか、見つけた子育て法というのは一体何だったのか、これは何が違うのか、どんな良いことがあるのか、誰でもできることなのか、を科学的データと自分の経験から書いています。その本が今日こうして皆さんと私を繋いでくれました。本当に嬉しいです。今日は私がたどり着いた教育法について、お話させていただきます。
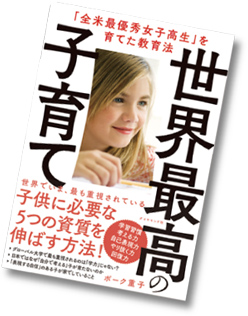

世界最高の子育てを探すきっかけ、それは娘を産んだときに「私のようになってほしくない」と、思ったことでした。私はそれまで何をやっても諦めやすくすごく中途半端で、例えば部活で選手から補欠になった途端に辞めてしまったり、学校のテストで点数が悪くなると諦めて勉強しなくなったり、就職しても「なんでこんな仕事しているんだろう」と感じたり「この仕事は私に合わない」とすぐに辞めていたりしていました。そんな私は自信がなくて自己肯定感が低い自分自身が好きではありませんでした。だから、私の娘には絶対にそうなってほしくないと願ったのです。そのためには良い教育方法を見つけなければならない。そう思って出産後すぐに行動に移したのですが、インターネットが発達する以前でしたから情報は今と比べるととても限られていました。でも私がラッキーだったのは、ワシントンD.C.という全米で最も研究機関が集まる場所に住んでいたということです。
また当時ちょうどアメリカで「非認知能力」という言葉が囁き出された頃でもあり、多くの研究機関が論文を発表していたのです。 英語で「Non-Cognitive Skills」と言いますが、非認知能力は数字では表せない能力で、やり抜く力、自己肯定感、自信、想像力、柔軟性、社会性、自制心、共感力、回復力、好奇心、主体性など生きていくために必要な人間力のあらゆる要素を含みます。聞き慣れない言葉でしたし、能力の定義が私が教わってきたものとは全然違っていて、私はこの「非認知能力」に非常に興味を覚えたのです。そこで「非認知能力」教育を実践している学校を探して見学に行きました。それが我が家とボーヴォワールという初等教育校との出会いです。
そして私はすごいショックを受けることになります。というのも、私が教室で目撃した教育はあまりにも非効率的に見えたのですが、しかし、とても楽しそうだったからです。確か小学校1年生くらいの教室の算数の授業だったと思いますが、1+1が2になること、それを50分の授業時間をまるまるかけて勉強しているのです。先生は子どもたちに「ここにりんごがあるわよ。りんごを使ってやってみようか? 花もあるし、ビーズもあるわよ」「自分がやりたい方法を見つけてね」と言いながら。私は50分もかけて「1+1=2」を教えるなんて非効率だと思って、そのことを授業後に質問したら先生はこのように言いました。「効率は問題じゃない。確かに1+1は2にしかならないけど、そのことを自分で発見することによって、子どもたちの心に喜びが生まれる。喜びがあると、好奇心が生まれ、自己肯定感や自信もわいてきます。そうやって私たちは子どもたちの中に強い心を育んでいるのです」。また先生はこうも言っていました。「非認知能力を伸ばせば認知能力と言われる従来の学力は自然とついてきます。難しい問題にぶち当たっても諦めずにやり遂げ、柔軟な心で解決法を探し、やりたくないときでも自制心を発揮してやりとげる子どもが学校の勉強くらいできないわけがない、そうは思いませんか?」
その瞬間「これが私が求めていた世界最高の子育てだ、私が目指す子育てに必要なのは非認知能力だ!」と、確信したのです。
日本でも今、非認知能力は文部科学省や学校教育の関係者で注目されるようになっていますが、そもそもの発端は1960年代にさかのぼります。当時、政府の依頼を受けてシカゴ大学のジェームズ・ヘックマン教授が、子どもに対する教育方法の研究を始めました。その後ヘックマン教授は2000年にノーベル経済学賞を受賞しています。
研究ではまず、当時の3歳児を幼稚園に行く子どもと行かない子どもに分け、6歳の時点でどうなったかを調査しました。その結果、幼稚園に行った子どもはそうでない子どもに比べて学力が上だったことが分かりました。そこでアメリカ政府は初等教育の重要性を認知して税金を投入するようになり、早期教育や英才教育が始まりました。
ヘックマン教授はその後も調査を続け、子どもたちが9歳になったときの状況を調べました。そしたら驚くことに両方のグループの学力に差はなくなっていたのです。これは「早期教育は効果はあるけれども長続きしない」という定説が生まれる元となりました。ですが、その後子どもたちが40歳になったときの追跡調査の結果はもっと驚きだったのです。この2つのグループに大きな差が出たからです。まず、高校の卒業率は幼稚園に行った子どもの方が2割高く、犯罪率は2割低い。さらにマイホームを持った人は、幼稚園に行ったグループが約3倍、月収2,000ドル以上の人が4倍となっていました。9歳の時点で学力に変わりはないのに40歳のときにこれだけの差が出るのは、一体何が原因なのか。ヘックマン教授が結論付けたのは、幼稚園のときにみんなと一緒に過ごすことで身につけた社会性や協働力、それに自分で難しい問題を一生懸命やり遂げることによって得た自信や自己肯定感、やり抜く力、それから、やりたくなくても宿題をきちんとやることなどで育んだ自制心。それらが総合した非認知能力を身につけたからではないか、ということでした。

見学から2年後、娘は4歳から9歳まで非認知能力の教育法を行っている初等教育の学校、ボーヴォワールに通うことになります。そこで入学初日に次のように言われました。「我が校は子どもの非認知能力を育むためにレスポンシブ・クラスルームというメソッドを採用しています。これは学校だけでなく、家庭でも実践していただくことが大切です。なぜなら、子どもは学校で時間を過ごしますが、それよりももっと多くの時間を家庭で過ごします。家庭というコミュニティの影響力は学校よりも非常に大きい。だからこそ、家庭でもレスポンシブ・クラスルームの教育法を実践していただきたいのです」。
我が家は非認知能力を伸ばすためのレスポンシブ・クラスルームを家庭でも10年間、真面目に実践しました。私は根が非常に真面目ですから、やるとなったらきちんとやるのです(笑)。今日は、このレスポンシブ・クラスルームというメソッドを、我が家でどのように実践したのかご紹介いたします。皆さんにもご家庭で試していただけたら嬉しいです。
レスポンシブ・クラスルームは認知能力重視の教育が中心だった1980年代のアメリカで、認知能力ばかり伸ばす教育をしていたのでは子どものためにならないのではないか、と危惧した数名の先生が集まって新たな教育法を模索したことに端を発します。そこから大学の先生や研究機関とチームを組んで新しい教育法を開発しました。それがレスポンシブ・クラスルームです。
この教育方法は本当に効果があるのか、私も興味があって調べてみました。最も知られているのは南部の名門バージニア大学と米政府の共同研究で、レスポンシブ・クラスルームのメソッドの有用性を確かめた研究です。バージニア州の公立校から無作為に選んだ28校を対象に、レスポンシブ・クラスルームを採用したクラスと採用しないクラスを分け、約3年間経過を観察しました。結果は、レスポンシブ・クラスルームを採用したクラスの子どもたちは学力が向上しました。そしてクラスの雰囲気が良くなり、いじめが減って、さらに先生の質が上がったそうです。非認知能力を伸ばすと、自然と学力が上がることが証明されたわけです。