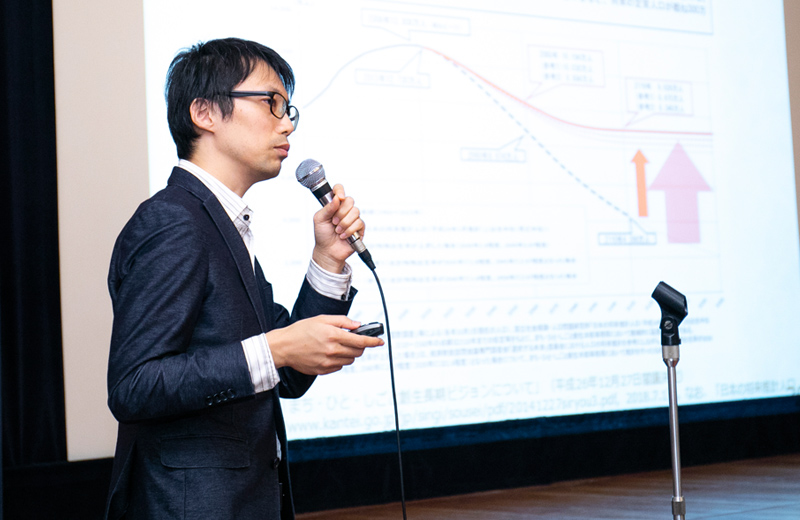「少子化時代における子育て支援の意義」
京都大学 大学院人間・環境学研究科
准教授
柴田 悠 氏
講演録 1
京都大学 大学院人間・環境学研究科
准教授
柴田 悠 氏
皆さん、こんにちは。お集まりいただきありがとうございます。
私は統計分析を使って政策の効果を研究しております。
今日は、今の日本の少子化のどこが問題なのかをお話しします。
また後半では、皆さんに身近な育児や教育の話もいたします。
今の日本の少子化の一番の問題は、進行のスピードが速すぎることです。子どもが減ること自体は実はあまり問題ではなく、減少のスピードが速すぎることが問題なのです。少子化のスピードが速すぎるので、一気に高齢化が進んでいきます。今のままいけば、2060年から高齢化率38%という、これまで人類が経験したことのない大変な状況になります。そうなると社会保障支出など、政府の使うお金がどんどん増え、財政が逼迫していきます。それに対応するために、政府は社会保険料を上げざるを得ません。私たちの支払う社会保険料が上がり、どんどん給料から引かれるようになります。そうすると私たちの生活費が厳しくなります。
あとは人手不足になります。これから生産年齢人口は減っていきますが、特に医療介護の人材の需要はますます増えていきます。ですから、ますます人手不足が加速します。今ですら人手不足ですが、これからさらに悪化して大変なことになります。とくに、介護を誰がするのかといった問題が深刻になります。
では、それを解決するにはどうしたらよいか。それは次の3つにまとめられます。
まずは、少子化のスピードが速すぎるのが問題ですので、人々の結婚や出産の希望を叶えることで出生率が上がる余地があるのであれば、そういう環境を整える必要があります。次に、財政が悪化していきますので、やはりAIや機械を使って労働生産性を高めたり、省人化を進める必要があります。また、教育の質を高めていく必要もあるでしょう。3つ目として就労支援があげられます。女性や高齢者を含めたさまざまな人々の中で、働く意欲と能力があっても働くことができていない方々がまだいらっしゃいます。そういった方々の就労を支援することも必要でしょう。
ではそれら対策の現状はどうなっているかを見てみますと、まず出生率は近年上昇していません。ここ数年、下降傾向が続いています。もし人々の結婚や出産の希望を叶えることで出生率が上がる余地があるのであれば、そのための環境を整えることは非常に大事です。そのためにどういう政策が必要かは、後でお話しします。
もう1つ。AI化や機械化、就労支援はすでに進んでいますが、しかし教育に関して見ると、まず育児の面で父親の育児参加が日本は非常に少ない状況があります。教育のリソースとして父親というのはとても重要なのですが、その父親が日本では育児参加をあまりしていない。つまり家庭での父親活躍が進んでいない。これが問題だと思います。
さらに、幼児教育の一種としての保育について見ても、3歳未満の時期に、保育を受けている子どもは日本では少ないのです。3歳未満では、多くの家庭で、主にお母さんが一人だけで子どもの世話をするという「密室育児」が行われており、お母さんの育児ストレスが高まりやすい危険な状態にあります。育児ストレスが高まれば、子どもの健全な発達を脅かす「不適切な養育」や「虐待」が生じるリスクが高くなります。この孤立育児の状況は、果たして子どもにとって良いことなのだろうかという問題があります。つまり、3歳未満での保育をどう考えるべきか、これがもう1つの問題としてあります。それらをどうすべきか、これから順に考えてみたいと思います。
まずは最初の出生率の話です。まず、どのくらい出生率が上がれば、将来の日本社会がより安定的になり、持続可能性が高まるのか。日本政府が、もし2045年までに出生率が2.07まで上昇したらという仮定で各種の推計を出しています。それによると、65歳以上の高齢者の人口比率、つまり高齢化率は、今は28%程度で、このままいけば2060年からは38%以上と、これまで人類が経験したことのない大変な社会になるわけですが、もし出生率が2045年までに2.07にまで高まったら、2090年以降は高齢化率は27%ほどで定常状態となります。つまり、今と同じ水準で落ち着くのです。ですので、今と同じくらいの高齢化率で落ち着くためには、出生率が2045年までに2.07まで上がる必要があります。
では、どうしたら出生率が上がるのでしょうか。産みたい人が産みやすくなったり、産みたいという気持ちが少しでもあった場合に、その気持ちを持ち続けることができるような環境に、どうしたらしていけるのか。まず基本的なデータを確認します。
なぜ出生率が下がっているのか、これには結婚率が関係しています。夫婦の間で生まれている子どもの数は実はあまり変わっていません。その一方で、結婚率が急激に減っているのです。結婚する人が急激に減っているので、出生率が減っているのです。日本ではとりわけ婚外子が非常に少なく、数パーセントです。日本では子どもを産むということは結婚が前提だという意識が非常に強いので、結婚しないと子どもを産みづらいという状況があります。そういう状況で結婚率がどんどん下がっているので、出生率が下がっているという結果になっています。結婚の背景にはもちろん雇用などの問題があります。それら結婚前からの状況も含めて、環境を整えなければいけないでしょう。
これまで日本で行われてきた、出生率や出生数、あるいは出産に関するさまざまな先行研究を概観すると、出生率の上昇には、さまざまな要因が関係していることが分かります。まずは雇用です。男女の雇用が安定していると、結婚や出産が起こりやすい。また、夫の労働時間や通勤時間が短いと、出産が起こりやすい傾向があります。また第1子での夫の育児時間が長いと、第2子が生まれやすい傾向があります。また最近の研究によれば、都市部では、親と同居や近居をしていても出産に結びつかないという結果が出ています。あとは教育費や住宅費が安い、育休を利用しやすい、地域の保育定員が多い、という要因が出産につながりやすい傾向があります。ここで特に注目したいのが、夫の残業時間、通勤時間、育児参加、それから、教育費や保育の状況です。というのも、これらは政策で改善できる余地があるためです。働き方改革や、高等教育の学費軽減、待機児童の解消など、政策で工夫できる余地があります。実際に今の政府もそういった方向ですでに動いているところです。
では、2045年までに出生率が2.07まで上昇するという状況がもし起こるのであれば、それはどういう環境を整えたときなのか。私は、先進諸国のデータを分析して平均的な傾向を導き出し、それを日本に当てはめて試算をしました。2045年まで今後27年間かけて、働き方改革で労働時間が短くなるとどうなるか、専門学校を含めた高等教育に通っている学生全員に一定額の学費軽減をしたらどうなるか、待機児童を完全に解消したらどうなるか、それらをインプットの情報として設定して、2045年の出生率に与える影響を試算しました。
労働時間は2045年までに週7時間程度減る計算で入れています。現状でも労働時間は減っていますが、27年間で週7時間減ると言う数字は、現状の1.5倍くらいのスピードで取り組まないと実現できない数字です。そうすると出生率は0.62高まる計算となります(ただし前提として、パートタイムとフルタイムの間での同一価値労働同一賃金がヨーロッパ並みに進む必要があります)。これに加えて、専門学校を含めた高等教育の学生全員に対して一人年間61万円の学費軽減(国立大学なら無料に、私立大学・専門学校ならほぼ半額になリます)をして、57万人分の待機児童を解消すると、あくまで計算上ですが、2045年の出生率が2.07に達する見込みとなります(なおここには日本だけで見られる出生率の減少傾向も加味しています)。
つまり、経済的に無理のない形で労働時間が大幅に減って家庭の時間が取れるようになるし、高等教育費も無料や半額になるし、待機児童も全くなくなるという環境になって初めて、日本社会の持続可能性にとって十分な出生率に初めて到達する。そのくらい大掛かりな政策を行わないと、日本の高齢化率はどんどん高まり、社会の持続可能性がとても危うくなるといえます。
もちろん、これはあくまで先進諸国のデータを使った推計で、先進諸国の平均的傾向に基づいた単純な試算ですので、これが果たして今後の日本にどのくらいあてはまるのかは、疑念が入り得るところです。ただ、あくまで1つの参考として、有権者や政治家、官僚のみなさんの耳に届けばと思っています(以上の少子化対策については詳しくは『週刊エコノミスト』2018年8月14・21日合併号と2018年8月28日号に自筆記事としてまとめてあります)。