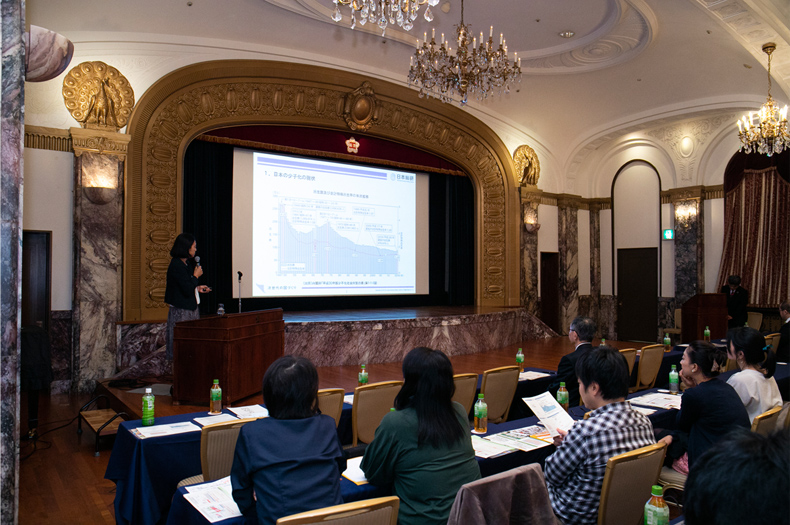「日本の子どもは幸せか」
~海外の子ども関連施策の動向~
日本総合研究所調査部
主任研究員
池本 美香 氏
講演録 2
日本総合研究所調査部
主任研究員
池本 美香 氏
今日は「日本の子どもは幸せか」という、これまで付けていないタイトルにしてみました。
今の日本の子どもが幸せとか不幸だとかを言うつもりはなく、
私は海外の子どもの政策を見る中で、日本の検討の中にそもそも
日本の子どもの状況はどうなのか、幸せなのか、そういう問いかけ自体がないことを
常々感じてきましたので、今日はそういうタイトルのもと、
海外では日本と違ってどのような検討や対応がなされているかといった
情報提供をさせていただきたいと思っております。
まず、基本的なこととして出生数や合計特殊出生率が低下しています。私が生まれたのは丙午(ひのえうま)の年※で、この年の出生率は1.58と、前の年の4分の3と特に低い水準でした。そして、私が就職した次の年に発表された1989年の出生率が1.57で、過去最低の1.58を下回ったことで、世間で「1.57ショック」と騒がれ、そこから少子化対策が始まりました。私は、自分の生まれた年と比較されていることもあり、ずっと少子化に関心を持ち、ここ30年くらい少子化対策、あるいは子どもや女性の政策についてリサーチをしてきました。最近は保育園の待機児童対策が注目されていますが、すでに5歳未満の人口は減ってきています。今後の出生数に関して、政府は2065年の出生率が1.44の場合を中位、1.65を高位として2種類の推計を出しています。しかしすでに、産む年齢の女性の人口が減っていますので、出生率が多少上がっても、生まれる子どもの数は増えないという状況です。従って、出生率が高めに1.65くらいまで回復するという前提でも、5歳未満の人口が減り続けることはほぼ確実な状況となっています。
ではなぜ少子化が進んでいるかというと、結婚していない男女が増えていることが一番大きいといえます。今30代後半の男性で、結婚していない人が3人に1人くらいになっています。特に、女性で子どもが生まれる確率が高いのは20代後半ですが、その年代の6割が未婚です。これでは子どもが多く生まれるはずがありません。女性の30代後半でも23.9%、4人に1人くらいは結婚していないのが現状です。
※丙午:干支の一つ。これにあたる年は火災の発生が多く、またこの年に生まれた女性に対しての良くない迷信があった。その影響で出生率の低下がみられた
政府がやってきたことを振り返ると、最近話題になっている待機児童ゼロ作戦は2001年からやっています。1989年の1.57ショックをきっかけに、1995年からエンゼルプランという子育て支援が始まっています。ちなみにその少し前、1986年に男女雇用機会均等法が施行されています。このため、女性が男性と対等に働けるように、働きながら子どもも育てられるように、保育を増やすという全体のフレームが描かれたわけです。3歳未満の保育や、残業にも対応する延長保育などから着手して、それから待機児童ゼロ作戦、ワークライフバランスと、仕事をしながら子どもも産み育てられるように施策による対応も進んでいます。最近では子育て安心プランといって、2020年度末までに待機児童解消が目指されています。学童保育、放課後児童クラブについても、放課後子ども総合プランで国は30万人分増やし、さらに最近出した新プランでは、追加で30万人分整備するとしています。このように、とにかく受け皿をどんどん増やしていこうという流れが中心となっています。

企業に対しても、従業員の子育て支援に積極的に取り組んでいる企業を認証して、認証を受けると「くるみんマーク」が使えます。私の名刺にも印刷されていますが、企業においても仕事と子育ての両立支援が進められているのが現状です。
政府が待機児童解消を進めてきた成果として、保育の量がものすごく増えています。待機児童がなくならないのは政府が保育施設を作っていないためだ、というイメージをお持ちかもしれませんが、実際の定員はものすごく増えています。平成27年からは保育の制度が新しくなり、自治体が必ず住民の保育ニーズを調査し、それをもとに保育の整備計画を立てることになりました。これに全市町村が取り組んでいることもあり、全体の定員がどんどん増えてきています。しかし、待機児童数はだいたい2万人くらいをキープしているという状況が続いています。これだけ施設を増やしても、保育所に入りたい子どもがそれ以上に増えているという状況です。理由はなぜかというと、1、2歳児の保育園の利用率増加です。私は今、子どもが中1と小2で、10年間保育園のお世話になりました。上の子が保育園に入った12年くらい前は、保育園に入るのは特別な人で、「保育園なんて、かわいそうだね」などと周囲の人に励まされるような状況でした。それが今では1、2歳児の47%、2人に1人くらいが保育園に入るほど利用率が上がっています。
こうした背景には、女性が働く割合が増えていることがまずあげられます。最近発表された育児をしている女性、未就学の子どもがいる女性の有業率のデータがありますが、この調査では2012年と5年後の2017年を比較しています。その5年間で、各県とも上昇幅がかなり大きいことに私はびっくりしました。兵庫や神奈川は専業主婦率が高い県でしたが、そこでも20%くらい有業率が上がっています。母親が働いていて、子どもを保育園に預けることが普通になりつつあるといえます。
もう1つ、ここで起きている事実としてご紹介しておきたいのは、保育士不足です。これだけ急激に保育利用者が増えますと、保育士も必要になります。数年前に保育士不足が騒がれ、最近はあまり騒がれなくなりましたが、それでもデータで見ると1人の保育士に対して求人数はどんどん増えています。最近の報道でも、施設をオープンしようとしたけれど保育士が確保できず始められない施設も出ているとありました。
保育の質も問題です。保育施設における死亡事故は毎年起こっています。最近では、全く保育経験がない保育士の割合が高かったり、新しい保育事業者が参入したりと、保育の質に対する不安が高まっています。政府も問題視して、保育園にビデオカメラを設置したり、なぜ事故が起きたか検証を義務付けたり、いろいろな対策行われています。
また、園庭などの土地を増やさずに入園児の量を確保する必要から、一部の保育園ではビルの中に施設を作ったりもしています。特に東京都は、認可保育園であっても園庭がない施設が多くなっています。また、保育園を建てるとうるさくなると近隣が反対するので、仕方ないから防音壁を作ったり、窓を開けないようにする施設も増えています。海外の方を日本のそういう施設に案内すると、「人権侵害ではないか」という意見も出るそうです。このように、保育を受ける子どもにとって厳しい状況も起こっています。
放課後児童クラブに関しても触れさせていただきます。保育園に行く子どもの割合が高まれば、小学校で学童保育を使う子どもの割合も増えます。小学生の数はどんどん減っていますが、放課後児童クラブ、学童保育の利用者数は増え続けていて、100万人を突破しています。学童保育の待機児童はあまり話題になっていませんが、保育園と同じように2万人弱の子どもが学童に入れない、だから親が仕事を続けられないといった状況が起きています。
学童保育も保育園と同様、数の増加で質の低下が懸念されています。実際、放課後児童クラブの大規模化が起こっており、今、71人以上の集団となっている施設が1,300ヶ所程度あります。さらに100人を超えるところも出ています。国としては、大規模集団は子どもにとってストレスになるので40人以下にしましょうという指針を出していますが、それでも71人以上の集団で運営されるケースが多くなっています。そういう状況は、子どもが過ごす環境としては非常にストレスが多い状況といえるでしょう。
小学校における暴力行為も増えています。暴力行為の発生件数の集計によれば、最近また伸び率がぐんと上がっています。昔の中学校の校内暴力のようなことが小学校で起き、低学年から授業が学級崩壊のような状況になっている学校もあり、今小学校では問題になっています。
これも最近の話題となっていますが、子どもの貧困について。学校教育を受けるにあたって必要なものが、家庭の経済事情で買えない場合には自治体が援助する制度がありまして、その就学援助制度を利用している子どもが小中学生で15%くらいまで増えて高止まりしています。政府も貧困対策を進めていますが、子どもの間での格差が大きくなってきている現状もあります。
児童虐待も心配です。児童相談所に児童虐待の相談があった件数が、一貫して増えています。
また、孤独を感じると答えた子どもの割合の調査で、なぜか日本だけが突出して高くなっているというデータもあります。国際比較の調査は、国民性などもあり簡単に比較できないにしても、子どもたちの学校での生活や教育も影響しているのではないかと思われます。「指導死」という、学校の指導によって子どもが死んでしまうことも最近報道されていますが、子どものための学校運営がなされているのかという点も気になります。
自殺率について。私があらためて調べたところ、15から34歳と少し高い年齢層ですが、自殺で死んだのか事故で死んだのか見ると、海外はだいたい事故の方が自殺より多いのに、なぜか日本だけ事故より自殺が多く、自殺率も高くなっています。なぜ多いのか原因究明をきちんと行うべきと思っています。